幼年期の終わり
アーサー・C・クラーク(著)
福島正実(訳)
SFの名作として知られている本作の感想をあえて2019年の現在に書いてみようと思う。
結論を言ってしまうと、本当に名作だった。(笑)
『幼年期の終わり』の概要
『幼年期の終わり』は、SFという枠組みを通して、人類とは何か?を問う傑作である。
本書は3部構成となっている。
第1部「地球とオーバーロード(上帝)たち」
第2部「黄金時代」
第3部「最後の世代」
読み終えて残る言葉は、第1部のタイトルにもある「オーバーロード(上帝)」だろう。
小説の時代背景は、人類がまだ地球から宇宙に飛び出していない時代だ。その人類がこれから宇宙へ飛び立とうとする矢先、地球に巨大宇宙船が飛来する。そして人類に呼びかけるのだ。「人類ははもはや孤独ではないのだ」と。
圧倒的な力を持つ宇宙船の声の主は、カレルレン。
「オーバーロード」とは、カレルレンをはじめとする圧倒的な科学力を持った彼らの呼称だ。
この手のSFだと突然飛来した宇宙船が人類を破滅に追いやるといったストーリー展開になりがちだが、『幼年期の終わり』の宇宙人カレルレンは、全く違う。地球の全世界の人々に対して、今後は争う必要などない事を伝えるのだ。
その巨大宇宙船を打ち落とそうとある国が反抗を企てるが失敗に終わる。
カレルレンは地球に対して静かな統治をおこなっていく。人類の悪癖である戦争を禁じ、人種差別を禁じるのだ。もちろん反抗する国もあるが、圧倒的な科学力をみせつけて(しかも平和裏に)人類の悪癖をやめさせていく。結果として地球は以前とは比べ物にならないほど平和になり、人々の生活も向上していく…といった展開で第2部「黄金時代」へとつながる。
実は第1部では、カレルレンたち宇宙人は何十年間も人類の前に姿を見せない。それに対する不信感が人類の一部で巻き起こってくる。
なぜ人類の前に姿を見せないのか?
これに対する人類の不満(もちろん我々読書の不満)は、第2部「黄金時代」で解消される。
カレルレンはじめオーバーロードたちが人類の前に初めて姿を見せるのだ。
なぜ、宇宙人たちは地球全体に平和をもたらしてくれたのか?
彼らの真の目的は何か?
これらが全て解き明かされるのが、第3部「最後の世代」となる。
福島氏の訳文は読みやすく、また『幼年期の終わり』の構成自体も段階を追って真実にせまっていくので、想像力が追い付かないといった事は決してない。
読み終えた後に残る部分
わたしは特に第2部「黄金時代」を読んだ際、人類とはなんだろう?という疑問が深くわいた。
もっと突き詰めて言うなら人類がしてきた事、これからするであろう事とは、一体どんな意味があるのだろう?という根本的な疑問だ。
第2部で描かれるのは、ユートピアのような人類の姿だ。しかし、本当に幸せなのか?という疑問が消えずに残る。
『幼年期の終わり』は、個人が星空を見上げた時にふと気づくような心の内を改めて考えさせてくれる小説である。
第1部に入る前の「プロローグ」部分が秀逸だ。
個人的にはこのプロローグ部分が一番好きかもしれない。わたしは本書を読み終えた後、またプロローグに戻って読んでしまった。
プロローグ冒頭で、ソ連とアメリカとに離れ離れになった宇宙開発者の友人2人が登場する。
時代背景は、ロシアがソ連だった時代。当時ソ連とアメリカの両大国は、宇宙開発にしのぎを削っていた。小説の時代背景もこれに倣っている。そう、人類はまだ月へも行っていないのだ。(実際にアポロ11号が月に行ったのは1969年だから小説が書かれた当時も人類は実際月に行っていない)
「人類ははもはや孤独ではないのだ」
この言葉で締めくくられるプロローグ。
本書を読み終えた後、郷愁を持って胸に響いてくる言葉である。
アーサー・C・クラークと本書について
わたし自身は著者のアーサー・C・クラークの名前をを小学校時代から知っていた。なぜならちょっと古い映画をテレビで放送する日曜洋画劇場などの番組で、何度もアーサー・C・クラークの映画『2001年宇宙の旅』を何度も放送していたからだ。
わたしが読んだのは早川文庫の福島正実氏が翻訳したバージョンだ。
読み終えた後、原作はいつ出版されたのかが気になったので(SF小説の場合、わたしはいつ書かれた本なのか凄く気になってしまう)調べてみると1953年にアメリカで初版が発行されていた。半世紀以上昔(というより、66年前!)に出版された本なのに読んでいてほとんど違和感がなかったことに驚く。まさにSFだ。翻訳した福島正実氏も凄い人なのだ、きっと。
ちなみに原題の「Childhood’s End」をGoogle翻訳にかけるときちんと『幼年期の終わり』と翻訳される。
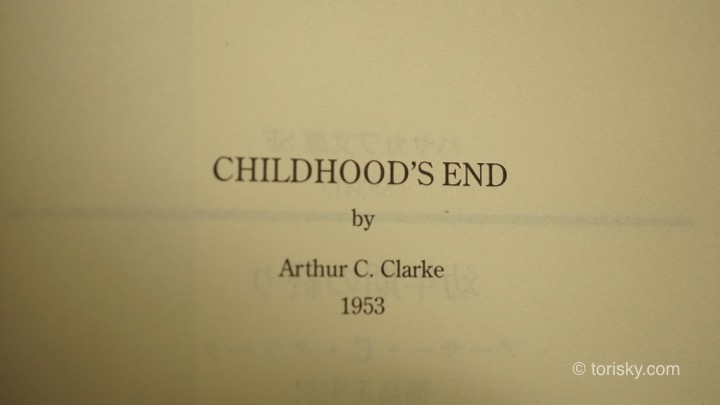


コメント