「あるうぅるるう!」
火星人の奇怪なさけび声が、わたしの耳に残っている。
SFの古典とも言われ、地球侵略をねらう友好的でない宇宙人がでてくる物語の代表格。
小学生のときこれを読んで、本当に宇宙人が襲ってきたらどうしようかと考えた本だ。
宇宙戦争
H.G.ウェルズ

1898年にイギリスとアメリカで出版された本。
2005年アメリカ映画「宇宙戦争」の原作にもなっている。
舞台は1800年代後半のイギリス。
宇宙から落ちてきた隕石と思われた物体が実は火星人の宇宙船で、そこから地球のクラゲに似た目だけが異様に大きい火星人が現れる。
火星人は圧倒的な科学力をもち緑の光線で地球を焼きつくす戦争兵器を持っている。
主人公の「ぼく」やイギリス軍はこれにどうやって対処するのか。
自動車や飛行機がまだ地球に登場する前のSF小説である。
移動には馬車か、汽車しかない。
そんな時代の話だ。
イギリスの郊外に落ちた隕石は一つまた一つと増えていく。
そこから火星人の操作する戦争兵器が出てくる。
火星人たちは、近づいた地球人を緑の光線で焼きつくしてしまう。
この本に登場する火星人はクラゲに似た目だけが異様に大きく弱々しい生物だが、火星人の作った戦争兵器や乗り物は地球の馬車や汽車、イギリス軍の大砲よりもずっと優れている。
ロボットやレーザー光線といった言葉さえまだ登場していない時代。
そんな時代に描かれた内容は、当時先進的だったと思う。
緑の光線はレーザー。戦争兵器は現代的にいうなら、ロボット兵器だろう。
現代であれば、インターネットなどの通信技術も発達し個人でも連絡や情報を得ることが出来るが、この時代にはそんなものはない。
イギリス軍でさえ、馬車に乗った一般庶民や着の身着のままで逃げてくる人たちに、向こうで何が起きているのかを聞いて判断している。
前半を読んだ段階では、地球は火星人のものになってしまうのでは、と絶望的になる。
後半に入ると形成が変わってくる。
地球上の「ある」ものが、火星人たちにダメージを与え弱らせていくのだ。
最終的に地球人を救った物が何であるかここで書くことはできないが、もともと地球にあって今もわたしたちとともに生きているものといえばいいだろうか。
100年以上も前に、レーザー光線、火星人の力を補うロボット、毒ガス兵器を登場させた作者の先見にも驚くが、それ以上にこの著者の言いたかったメッセージは、強烈だ。
この本に登場する学者がこんなことを言う。
「乗り物が発達すれば、足が退化し、栄養剤などが発達すれば、消化のための内臓はいらなくなって退化する。最終的には脳と、脳で考えたことを実行する手だけが進化しつづける。地球人も科学が進歩すれば、いずれ火星人のように脳と目だけが異様に大きい生き物に変化するだろう」
火星人たちのクラゲのような足は乗り物によって退化したもの。
歩けなくなった足を補うために、火星人たちはロボットを作り自分たちの足とする。
どこか今の地球の状況に似ていないだろうか。
わたしが、SF小説を好きな理由はもしかするとあり得るであろう未来を描いているからかもしれない。
主人公の「ぼく」は、最後にこう考える。
火星人たちに突然侵略され、あげくの果てに食料とされた地球人は、まるで自分たちが地球の自然や動物たちにしてきたことと同じだ、と。
牛や蟻たちからすれば、地球上の自然の生き物たちからすれば、人間は悪魔のような存在だったのだ、と。
人の気持ちになって考えなさい、とはよく言われる言葉だが、相手を「人」ではなく、「地球上の生き物」として考えたところにこの物語の先見性と想像力がある。
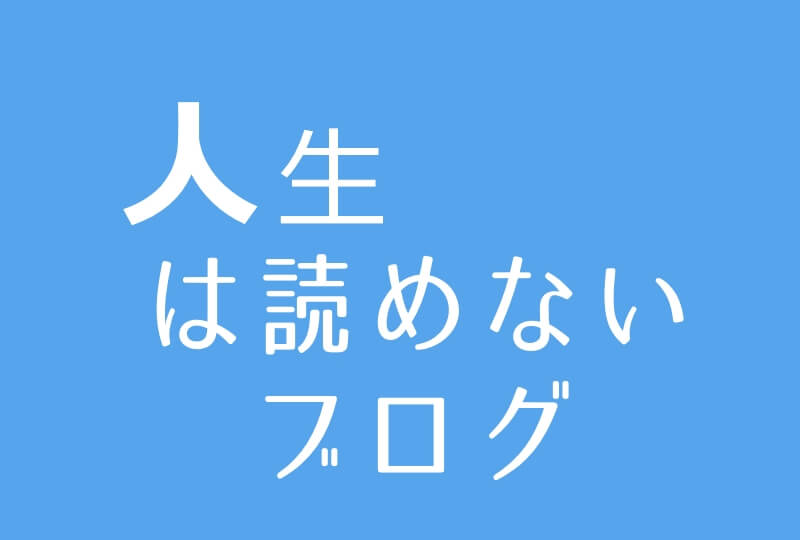

コメント