ぼくは戦場カメラマン
渡部陽一(作)
ぼくは戦場カメラマン (角川つばさ文庫)
それが「ぼくにできること」なのです。
と、この本の作者である渡部陽一は、最後に読者にこう語りかけている。
「人は何かの役割を持って、みな生まれてきた」という以前聞いた言葉を思い出した。
作者の渡部陽一は、大学1年のときの生物の授業でアフリカのピグミー族を知る。
ピグミー族は、いまだに狩りをして動物を捕まえて生活を送っている種族だ。
ただ、ピグミー族に会いたいという一心で渡部は、アフリカに旅をする。
ジャングルの中を2ヶ月もかけて横断しなければピグミー族に会えない。
ヒッチハイクをしている途中に乗せてもらったトラックが少年ゲリラ兵に襲われ、銃の持ち手で立ち上がれないくらいに殴られ帰国した経験が、彼のその後の人生を変える。
普通の人であれば、異国で立ち上がれないくらいに殴られれば「もうあそこへは、行きたくない」となるだろう。
世の中には、冒険心を持った人が少なからずいる。
作者の渡部もその一人だ。彼は、紛争中の地域の状況を、なんとか皆に伝えることが出来ないか、と考えた。
彼は、自分自身で「戦場カメラマン」と名乗っているだけで、「どこかの会社の社員カメラマン」ではない。
彼が大切にしている本は、冒険家「植村直己」がマッキンリー山で行方不明になるまでを描いた本「遥かなる人:植村直己物語」だ。
その本のキャッチコピー「冒険とは生きて帰ること」が、彼の取材のポリシーである「戦争取材とは生きて帰ること」につながっている。
自分の役割を知っている人は強いなあと思う。
この本の内容は、凄い体験のオンパレードだ。
ウォークマンと交換したカヌーのこぎ方を現地で3日間かけて習い、ザイール川をわたる途中でカヌーに穴があいて食べ物もつき、生死の境をさまよった際、助けてくれた原住民から食べものを頂く。
体長10cmで毛が5mmもある毛虫を食べた感想は、とり肉の味に似ているだ。そして、毛虫を咬んだときにでる体液は、焼き鳥のタレの味だ。
高山病で死にかけた体験。
マラリアに感染し、一生肝臓にマラリア原虫を飼うことになった体験。
紛争地域などで入国が困難なとき、入る前に現地の酒場やレストランに通い、何週間も普通に過ごし、現地の人で内務省に通じている役人と仲良くなり、プレスパス(現地で取材できる通行証のようなもの)を得る体験。
普通に考えたらなぜそこまでする、と言いたくなるような内容だ。
わたしなどは、戦場に行くことすら躊躇すると思う。
まして、異国の地で自分自身が死闘してまで得たいものとはなんなのだろう。
しかし「ぼくは戦場カメラマン」のタイトル通り、渡部陽一は、まさに「戦場カメラマン」なのだ。
児童書ということもあり、「なぜその地域で戦争をしているのか?」を、平易な言葉で説明もきちんとしており、世界情勢の入門書としても良書だと思う。
読み終わった後、「自分が、この世界で出来ることはなんだろう」と考えさせられる。
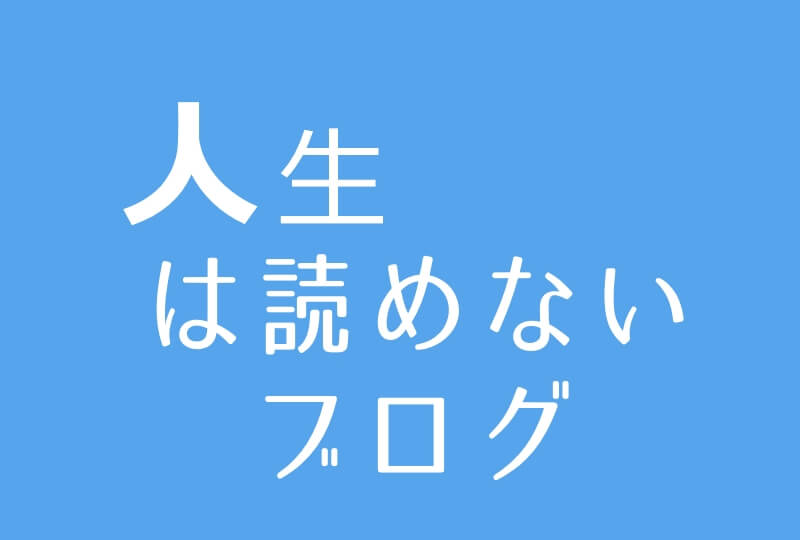


コメント