きっと「したく」というのは、なにかがあってからするものではないのです。それでは、まにあわないものなのです。 ―本文より
ひとりたりない
今村葦子(作)・堀川理万子(絵)

この本の副主人公である「おばあちゃん」のとった行動は、わたしたちが人生においてせっぱ詰まったとき、にっちもさっちもいかなくなったときの解決方法を教えてくれる。
小学五年生の女の子琴乃(ことの)が主人公だ。
本の表紙にあるように弟がいる。なぜ二人が前を向いて手を握っているのかはこの物語を読むとすぐにわかる。
わたしは、『ひとりたりない』という題名に惹かれ、この本を手に取った。
児童向けのミステリーかと思って読み始めた。しかし、違った。
冒頭を読み、この本が
「いつもいるべき人がそこにいない」
という悲しい話だと気づいた。
家族や友人。いつもそこにいるべき人が、ひとりでも欠けたら?
想像の中で大事な人をひとりけずってみる。とても怖い想像だ。
ばらばらになってゆく家族のSOSを主人公の琴乃は「おばあちゃん」に求める。
わたしが一番残った言葉は、主人公琴乃の心の中の声だ。
私は夜、どこかにいって電車にのっているときなどに、遠い家々の窓のあかりを見ると、なつかしいような、かなしいような、ふしぎな気もちになることがあります。
わたしも他人の家の窓あかりなどを見たときに、あたたかいのだけれど、どこかさみしい気もちになることがある。
何かを思い出しているのかもしれない。
帰宅したとき、家の明かりがついていて「おかえり」といってもらえることは嬉しいことなのだ。
窓のあかりで心も明るくなる。そう素直に思う反面、夜窓からもれるあかりは、もう二度と戻らない過去をみているようでもある。
あたりまえのことをふつうにするといった行為はやさしいようでいて難しい。
本書では、おばあちゃんの行動をとおして、そして『ひとりたりない』天国のおねえちゃんをとおして、あたりまえの大切さ、ふつうでいることの大切さを教えてくれている。
おばあちゃんは手料理を作って家族を待つ。
料理を作ること。
食べること。
そこに「誰か」がともなって美味しくなるのだ。
「まにあわせ」でない時間をかけたものに人の心は動かされるのだと、あらためて感じさせてくれる本だ。
本書では、おばあちゃんも天国のおねえちゃんも整理が得意だ。
きっと「したく」というのは、なにかがあってからするものではないのです。それでは、まにあわないものなのです。
「したく」はいつも「何か」の前にする。
よくよく考えてみると、人生はいつも「何か」の前段階だ。
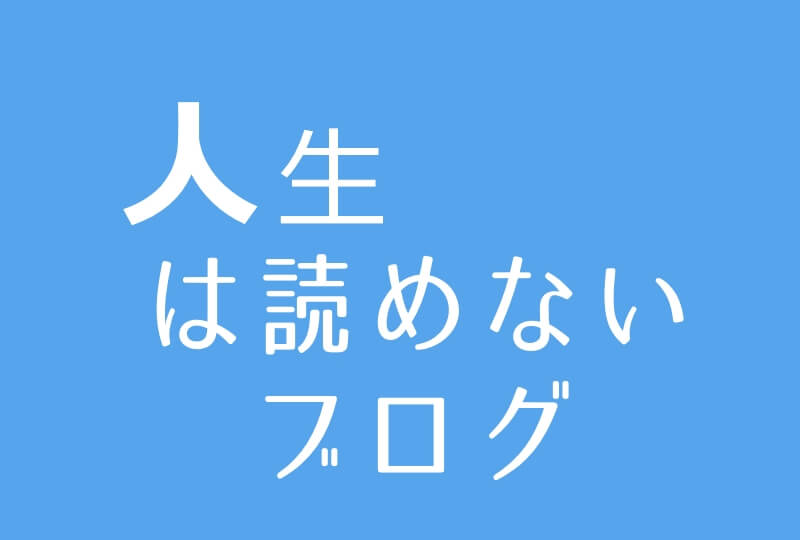

コメント