大往生したけりゃ医療とかかわるな
中村仁一(著)

わたしは、医療や薬に関しては、素人だが、この本を読んで、普段あえて勉強をしたくもない「薬」や「医療」について以前より恐くなくなったと感じた。
何を恐れていたかというと、「薬」や「医療」に対しての「つきあい方」だ。
著者が言う「死に方を考えることは、生き方を考えることである」という言葉にも、きちんとした実践からくる解説がなされていて興味深い。
決して病院には行くな、という内容の本ではない。
ただ、「熱がでたから」とか「お腹がいたいから」とか、ちょっとしたことでいちいち病院にかかり薬をもらっていたのでは、自分の身体のことを自分自身で判断できなくなってしまいますよ、ということは最初に断言してある。
参考になったつきあい方。
薬について
薬を飲んで治るのではない/薬は自然治癒力の補助でしかない
医療にたいして
大学病院ほど信頼できる医者がいるわけではない/マスコミに登場する医者や本を出している医者がいい医者ではなく世渡り上手なだけ/教授や博士とつく医者だから手術が上手とは別/リハビリすればもとにもどるのではなく、あくまで元の状態に近づくだけ
すべてわたしたちの勝手な「思い込み」からくることだ、と著者は説いている。
もう1つ全体的な言葉をあげるとすれば、
「本人に治せないものを、他人である医者に治せるはずがない」だ。
人間には、本来自然治癒力があり、それが機能しなくなったときが死に時だ、ということだ。
「大往生したけりゃ医療とかかわるな」というのは、副題にある「自然死のすすめ」がその結論だ。
最新医療で苦痛を強いられる「死」を迎えたくなければ、生きているうちから「自然死」を考え、選択していったほうが苦痛も少ない穏やかな死を迎える事が出来ますよ、という意味だ。
苦痛も少なく、というのは、実際に著者が老人ホームでの自然死を看取ってきた経験からの話だ。
著者の第一希望の死は「がん」での自然死だそうだ。
余計な治療をしなければ、痛みはほとんどなく死ねるのだそうだ。
自分で食べる事ができなくなり、飢餓状態になった場合でも、本人はそれほど苦しい訳ではなく、モルヒネ物質がでてくるので、楽に死ねるのだとのこと。
本書は、昔から日本人が看取ってきた家族の「死」である「寿命がつきたら死ぬ」という自然死を最近は実践する事が難しくなってきているという警告書でもある。
本来、年寄りはどこか悪いのが正常
年寄りの最後の大事な役割は出来るだけ「自然に」死んでみせること
「逝き方」は、「生き方」
わたし自身、最近のアンチエイジングや健康食品、サプリメントなどの過剰な宣伝や反応に違和感を持っていた。
70年も使ってきたのだから、壊れて当たり前。
家電製品などは、10年もてばいい方だ。人間の身体はそれよりはるかに長く使える。
でも、いずれ身体も壊れるということを信じなくなっているのが現代人だ。
「年寄りで、身体のどこも悪くなかったら、それこそ異常」という著者の言葉は的を得ている。
「お金を出せば」とか「最新医療を用いれば」とか「いい病院にかかれば」とか私たちは、医療を「万能の神」だと勘違いしていたのだなぁと思う。
人生は「苦」である。
老いを病にすりかえて、死すらなんとかなると錯覚させられてしまったところに人類の奢りがあるのだ。
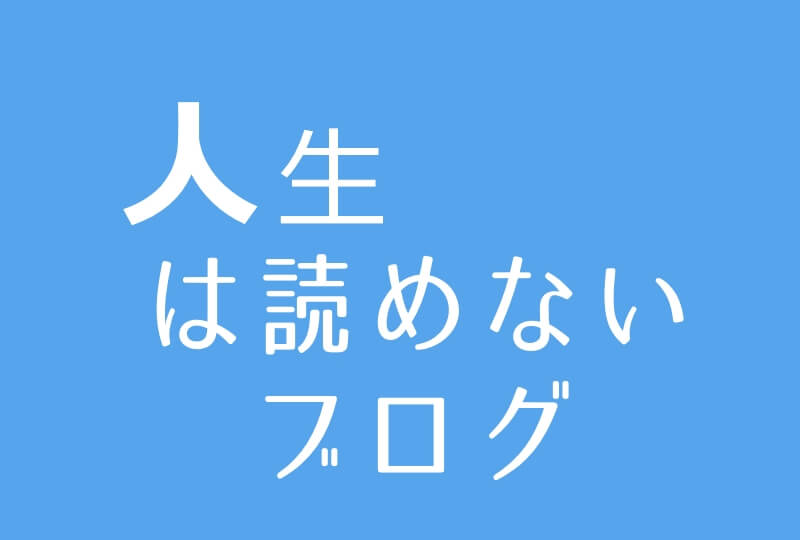

コメント