『果てしなき流れの果に』
小松左京(著)
人類が、自分たちを超える高度な文明に出会った時、一体どうなるか?
そんなSF小説はごまんとある。
『果てしなき流れの果に』もその一つだ。
自分たちを超える高度な文明に出会った時の人類というSFのジャンル(?)があるとして、『果てしなき流れの果に』はどのタイプだろう?
大昔ならHG・ウェルズの「宇宙戦争」みたいな地球人が火星からの侵略の危機に瀕する戦争タイプ。
少し時代が流れて、圧倒的に高度な文明が地球に降り立ち人類に平和をもたらすアーサー・C・クラークの「幼年期の終わり」のような非戦争タイプもある。
人間はしょせん、誰にもさばかれなかった。―もし、さばくものがあったとしたら、おのれでおのれをさばいたのだ。「種」の連帯のもとに、「自然」と対決することを、ながらく怠り―そのむくいとして、自然の突発的な異変に対処する力を、きわめて不十分にしか蓄積できなかった。
『果てしなき流れの果に』より
前半はミステリータッチに進むが、中盤からは「幼年期の終わり」を彷彿させる。
そして後半にかけては、前半謎だった部分がしだいしだいに紐解かれていく。
極めて日本的な終わり方。
宇宙や時間といった壮大なテーマを扱っていながら、最後はそう来たか!
人類とは何か?
歴史は人類にとって何であるか?
本書は壮大なテーマを持ちながらも、主人公たち個人個人の感情にもしっかり触れてくる物語となっている。
宇宙をテーマにしてしまうと物語の中の個人というものが見えにくくなるのだが、小松左京の小説にはきちんと個人というものが息づいているような気がする。いわゆる人間愛を感じる。
極めて日本的な終わり方、と言ったのは海外のSF小説では本書のように最後は「人」の「感情」で終わりとするものが少ないように思うからだ。
―だが、人間の〝認識する能力〟というものは、大変なものだな、ホアン。人間の認識能力は、人間の現実的状態の幸不幸に関係なく、とてつもなく、深遠で巨大なことを認識できる。しかし、その到達し得た認識は、その時の人間の状態を、ちっとも変えやしない。
『果てしなき流れの果に』より
わたしが一番印象に残ったのは、物語の中で誰かが叫ぶ「歴史を変えることはいけないのですか?」というセリフ。
「現在」の意味を考えされられる。

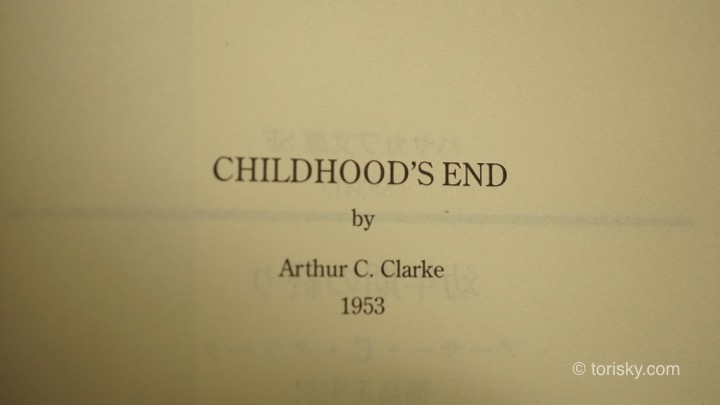


コメント