失われた時を求めて1 第一篇 スワン家のほうへ
マルセル・プルースト(著)
井上究一郎(訳)
いわずと知れたフランスの作家マルセル・プルーストの大長編小説。
わたしの読んだ本は、ちくま文庫の全10巻のうちの第1巻。
まずは感想
物語の展開を期待して読み進めようとするから挫折する。
物語小説として読んではいけない。
だって、主人公が、出てきた紅茶と菓子の味について6,7ページにもわたって述べてしまうような小説だ。しかも中世フランスの貴族社会が舞台とあっては1つ1つの言い回しが詩的にならざるを得ない。
ある本を読んでいるとき、その本に描かれている地方を訪ねることを両親がゆるしてくれたら、私は真実をかちとることに向かって貴重な一歩をふみだすように思ったであろう。なぜなら、人は、自分の精神にいつでもとりかこまれている、という感じをもっているにしても、それは…
「失われた時を求めて1」より
とこんな感じの文章が延々と続く。嘘じゃない。
とにかく一文が長い!
読点(、)がいつまでも続き、句点(。)は、はるか宇宙の彼方。
「理解するな、感じるんだ!」という読み方が適切か。
詩のような「。」の無い文章がいつまでも続いていく小説、といっておけば間違いはないだろう。
セリフもある。たまにある。
「2,3度ね!」などと恋人の短いセリフが来ようものなら、そのセリフを言った恋人に対しての主人公やらスワン氏(主要登場人物の一人)やらの考察や心情が数ページにわたり延々と続くのだ。
登場人物たちの人に対する考察と心情。
慣れてくると変態人物の内面をのぞくようで面白いときがある。
時折「ああ、そんなことあるある」などと納得し「ああ、おいらも変態だったのか」とうなずくことになるだろう。
最後に要約が載っているくらいだから、長すぎるんだろう、この本は。
1巻目の「スワン家のほうへ」を超約すると、
主人公やスワン氏の恋にからむ心情の吐露。
想像で相手に嫉妬したり、嫌われているのにもいいように取ったり。(スワン氏はストーカーだろ!)過ぎ去った日々への主人公の哀惜。
といったところ。
ところどころ気になる短文があったのでメモをしておく。
ひまなら読んでみるべし!
気になった短文
こうしてみると『失われた時を求めて』は、やはり詩的です。
それにね、坊ちゃん、一生のうちには、といってもあなたにはまだまだ先のことですが、こんなふうに思われるときがあります、すなわち、疲れた目が、もう月光だけにしか、耐えられないというときが、そして耳も、月光が静けさのフルートにあわせてかなでる音楽しかきくことができないというときがやってきますよ。
p213
それにしても、人間はどんなに人工的なものをつくる場合でも、自然に即してやるのである…
p229
人は自分が幸福なことに気づかない。誰でもけっして自分でおもっているほど不幸ではないのだ。
《中略》
人は自分の不幸なことに気づかない。誰でもけっして自分で思っているほど幸福ではないのだ、と。
p598
なぜなら、われわれが恋だと思い、嫉妬だと思っているものは、連続した、分割できない、同一の情熱ではないからだ。それらは無限に継起する恋、無限に異なる嫉妬からなりたっていて、その一つ一つはつかのまのものなのだが、多くのものがたえまなくあらわれるために、連続の印象、単一の錯覚を起こさせるのである。
p628
なおまた、単なる量の上から見ても、われわれの生活にあって、日々はたがいにひとしくはない。私のようにすこし神経質な人間は、自動車のようにいろいろ「スピード」を調節しながら、その日その日を経過してゆくのである。
p658
ある一つの映像の回想とは、ある一つの瞬間への哀惜でしかない…
p720
補足:本の厚さ
文庫本で本文が720ページあった。
ちなみに本文のあとに続く要約と注釈もけっこうなページ数を占めている。
ページの感覚で言うと…

わたしは嫉妬深いが憎めないスワン氏の恋あたりから少し面白くなった。
でも凄く面白いわけでもない。
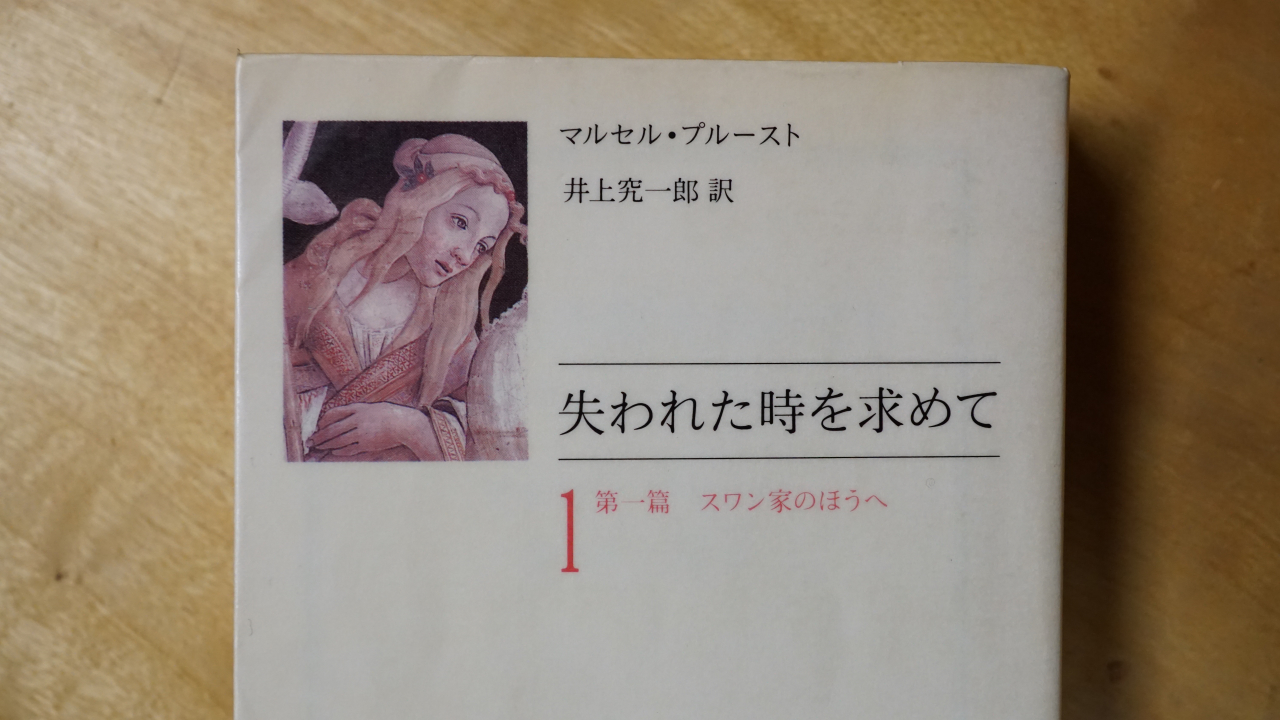

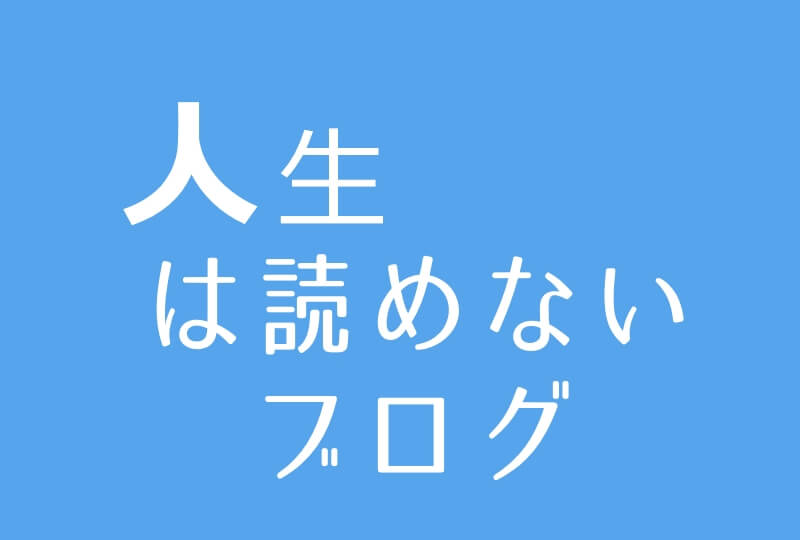
コメント