失われた時を求めて2 第二篇 花咲く乙女たちのかげにⅠ
マルセル・プルースト(著)
井上究一郎(訳)
「失われた時を求めて」は、一文が長い!そして一文が長すぎる故に途中から話が別の方向にそれていくことも多い。これは1巻から続く本書の大事なポイントだ。
2巻について
1巻では嫉妬の鬼スワン氏の恋が描かれていたが、今回はどちらかというと主人公の「わたし」の恋愛とスワン夫人との関わりが中心。
まずスワン氏の結婚相手に驚くほかない。
1巻では、スワン氏のオデットに対する嫉妬に驚愕したが、2巻では、主人公の「わたし」のジルベルト(ジルベルトはスワン氏の娘)に対する嫉妬も負けていないと感じる。二人の恋愛の結末はどうなるかは読んでのお楽しみ。
フランス貴族もつまらないことに気をつかっていたんだなあ、と感じざるを得ない描写が多数ある。
サロン(貴族同士の集まり)に誰を呼ぶか?サロンに呼ばれたけど〇〇さんが来るからどうしようか?などなど。
「失われた時を求めて」風の長い一文での感想
「失われた時を求めて」は、詩的な表現が延々とつづき、一文がしかも長いため理解を途中から放棄せざるを得ないことに加えて、原文はフランス語で書かれているわけだから、これを訳した井上究一郎氏はどれだけの労力をこの翻訳にかけたのかと思うと、わたしは氏に感服するとともに驚きを禁じ得ない。
名言集「失われた時を求めて2」
おそらく、ほとんど誰もが、恋愛という現象の純主観的な性質を理解していないであろう、また恋愛が創造する付随的な人格を理解していないであろう、その付随的な人格というのは、世間でかねて通用している姓名の本人とはまったくべつの存在であり、しかもその人格の大部分の要素は、われわれ自身のなかから抽出されたものなのである。
理論的には、人々は地球が回転していることを知っている。しかし現実にはそれを目にはしない。人々があゆむ大地は動くとは思われず、人々は静止のままで生きている。一生における時間に関してもまたその通りである。
さまざまな事件が、人生において、また人生の明暗に満ちた状況において、恋愛にからまって起こるが、そうしたすべての場合に対処する一番いい方法は、何も理解しようと試みないことである。
人がよく「はじめてきく」というのはけっしてうそではない。最初きいたときになんの印象もえなかった、と人はよくそう思っても、ほんとうに何も耳にとめていなかったのであったら、二回目も三回目も最初とちがわないであろうし、十回目にいたって理解を増したという理由もないであろう。思うに初回に欠けているものは、理解ではなくて記憶なのである。
子供が受けついでいる長所と短所とは、非常に奇妙に配分されているもので、一方の親の性質に不可分離のように見えた二つの長所も、子供はその一つしかもっていなかったり、またその一つが、それととうてい両立しないと思われた他方の親の短所の一つに、むすびついていたりする。ある精神的長所がそれと相容れない肉体的短所となってあらわれるということは、しばしば子が親に似る方法の一つなのである。
兵士は戦死するまでに、どろぼうはとらえられるまでに、また一般の人は死ぬまでに、まだ無限の猶予期間があたえられていると思いこむ。それこそ個人を――ときとしては民衆を――危険からではなく危険の恐怖から、実際には危険の念を抱くことから、まぬがれさせている呪符なのだ、しかしそのことが、場合によっては、勇敢になる必要なしに危険をおかさせているものなのだ。そんな種類の、しかもあぶない安心が、和解や手紙をあてにする恋人を力づけている。
結局旅行特有のたのしみは、途上で地面におりたり疲れたときにとまったりできる、ということではなく、またそんなふうに出発と到着とのあいだの差異をできるだけ感じられなくすることよりも、むしろその差異をできるだけ深く感じるようにすることにある、つまり、われわれの生活している場所から、希望の場所の中心へ、想像力が飛躍でもってもってわれわれを連れていってくれたときのように、二つの場所の距離の差を、思考にあったときのままに、完全に、そっくりそのままで、もう一度感じなおすことにある…
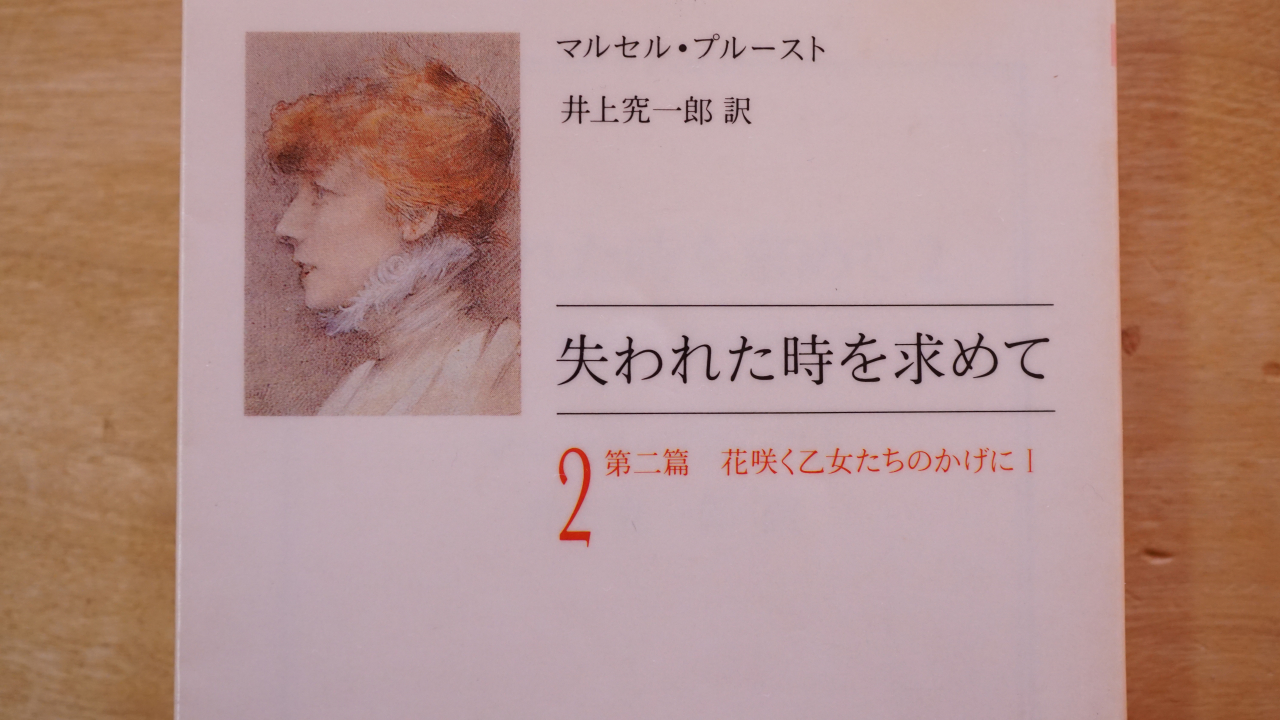

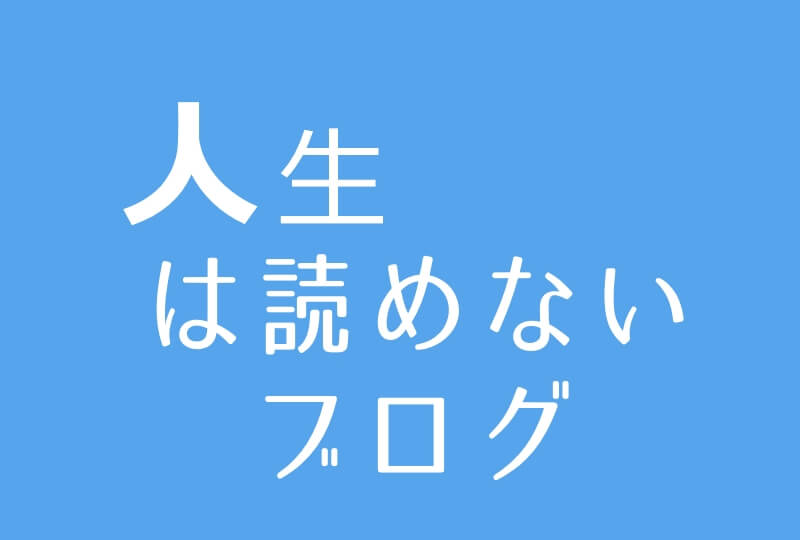
コメント