「サピエンス全史」という本がある。(冒頭から別の本の話で申し訳ない)
上下巻の大著で、人類の誕生から現代までを扱った壮大な本だ。「サピエンス全史」では、《文明は人類を幸福にしたのか?》という問いを歴史を振りつつ検証している。歴史上の登場人物や現代の人物が数えきれない程登場して、事実関係を元に文明と人類の幸福ついて論じた名著だ。
「流浪の月」には、主要な人物3名以外には数名しか登場しない。ただ、わたしには「サピエンス全史」と「流浪の月」が似通っていると感じたのだ。
かたや人文学書、かたや小説。共通項があまりにもないのだが、《人類の幸せ》というものについて今までに気づかなかった考え方を提供しているという点で両者は似通っている。
以下感想。
彼女と彼との物語。後からもう一人加わって、彼女と彼と彼女の3人の物語となる。
「わたしは、これを、なんと呼べばいいのかわからない。」
本書に何度か登場する《彼女》の言葉である。
この2人のあるいは3人の関係について《彼女》は何度か自問自答している。確かにこの2人、いや3人の関係を何と呼べばいいのだろうか、事実最後まで読み進めてもこの3人を表現する言葉が見つからないのである。
世間的に見ると3人が3人とも不遇な環境にある。世間的に見ると、と言ったのは登場人物の3人はマスコミや一般社会からすると、犯罪者(彼)とその被害者(彼女)と離婚して愛人がいる母親の子(もう一人の彼女)と見られてしまうからだ。ところが3人は一般に自分たちに対して貼られたレッテルとは違う意識を持って生きている。3人がそれぞれ別に暮らしていれば、たぶん《幸せ》ではない。3人が一緒にいられることが本書では《幸せ》の形となっている。
読み終えてわたしが一つ考えた事は、世間一般に言われる「不遇」を表すような言葉たちのこと。
「被害者」「片親」「浮浪者」等々、世間から不遇というレッテルを貼られた言葉たち。これらはあくまで《わたし》からの判定であって、本人たち判定では無いということ。何が幸せか?は本人にしか分からず、他人には判定できない。そうした当たり前の事を本書は気づかせてくれる。
設定が都合よすぎないか?と見る向きもあるだろうが、これは小説。
「ある事」を「気づかせてくれる」ためには「サピエンス全史」同様に小説でなくてもいい訳だが、読者をハラハラドキドキ楽しませながら「ある事」を「気づかせてくれる」力量が、著者凪良ゆう氏の力量なのだと思う。面白かったし、この3人の関係性が羨ましく感じた次第です。

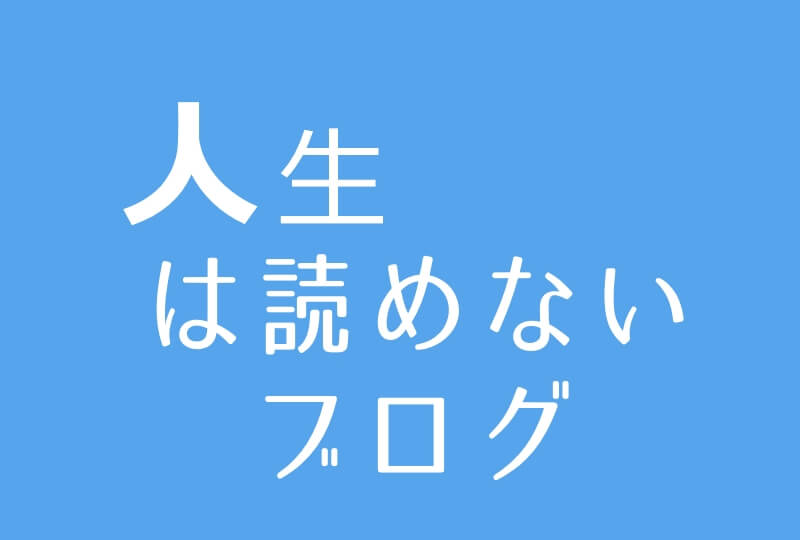

コメント