永遠のとなり
白石一文(著)
「人生も絵とおんなじぞ。上手に描けん、飽きた、つまらん、そげんこと言うて途中でやめるとが一番つまらんと。描き上げた絵は、時間が経ってから見直したら、どれもみんな味があるし、そんときは思いもせんかったようないろんな思い出ば連れて来てくれたりすると」
などというセリフがいきなり飛び出してくる所が、白石一文なのだと思う。

これだけ「生きるということ」「死ぬということ」に対して真正面から書いている小説家も現代では数少ないのではといつも思う。
それは数々の登場人物のセリフから十分に感じられる。
主人公の青野精一郎は、福岡出身。
一度は東京に就職し妻子もいたが、部下の自殺からうつ病をわずらい会社を辞め、現在は妻と離婚し地元に舞い戻っている。
協議離婚のため、子どもの進学金を工面するのに悩んでいる。うつ病もまだ完治していない為、現在未就職でもある。
主人公の友人「あっちゃん」こと敦は、癌を一度克服したものの結婚と離婚を繰り返している。
『永遠のとなり』は、この男二人を中心に展開する。
人生の終わりを感じさせる男二人が物語の中心である、それも「さえない中年」というところが本書の一番の面白いところだと思う。
誤解をおそれずに言うと、きっと多くの人が「読みたくない」と思う。
わたしは主人公に近い年齢なので、読んでみたくなったが、20代の頃であれば本書を手にしたかどうか。
読んでみたくなったと言ったが、「知ってみたくなった」の方が近い。
疑似体験したような、あるいは疑似体験してみたくなるような所が小説の良い所だ。
博多弁がこの小説に一役買っている。同じセリフを標準語で話されても味わいが少ない。
「どんなに上手くゆかんでも、とにかく最後まで描く。いつものとおりたい」
主人公の精一郎あっちゃんが山登りしたときにスケッチブックを開く場面での会話だ。
会話はこう続く。
「若い頃は、年寄りば見たら、ああこの人たちにも若い時代があったんやろうねえ、って思いよったけど、自分が歳取ってきたら、本当にそうやったやなって妙な実感が湧くようになったな…」
バブル崩壊後の日本に対して主人公がするシーン。
「私たちの欲望は次々と細切れにされ、その細切れごとに過剰なまでのサービスが用意され、充足させられていく。その一方で、もっと大きくて曖昧で分割できない大切な欲望、たとえば、のんびり自然と共にいきたいだとか、家族仲良く暮らしたいだとか、本当に困ったときは誰かにtっすけてもらいたいだとか、病気をしたらゆっくり休みたいだとか、ひとりぼっちで死にたくないだとか、必要以上に他人と競いたくないだとか、そういった水や空気のように不可欠な欲望はどんどん満たされなくなっている」
主人公を通して登場人物を通して著者は常にストレートに自分の意見を投げかけてくる。
わたしの一番心に止まったセリフがこれだ。
「だけど、いろんな町でいろんな人がこうやって生きてるんですよね。そんな無数の人たちを一人一人の身体に自分と同じようなうじゃうじゃした人生がみっちり詰まっているかと思うと、ときどき何とも言えない気持ちになります」
わたしはこの「うじゃうじゃした人生」という言葉が凄く気に入った。
どこかで使おうかと思っている。
わたしの持っている本書のカバー写真は、小学校の校庭である。
本書を最後まで読んだときに、ああそうか、と思う写真だ。
それはタイトル『永遠のとなり』についても同様である。
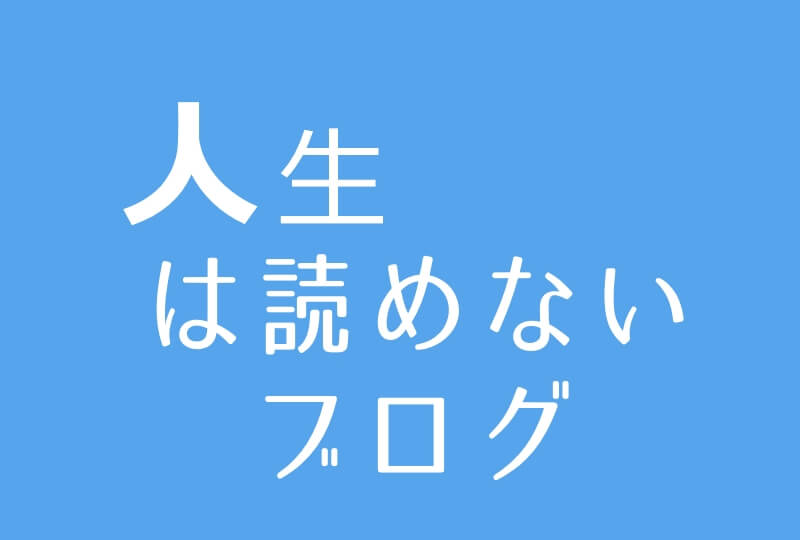

コメント