「たまたまが一生になることもある」 『64』本文より
64
横山秀夫(著)

「執念」というものを感じた。
人間の「執念」という言葉がぴったりくる推理小説だ。
最後の最後まで、この本に救いというものを見いださずにいたわたしは、読み終えた後に本書の残した救いが多岐にわたっていたことに気づいた。
時効間近にせまる未解決事件64には、隠された秘密があった。その秘密が次第に明らかになるにつれ新たな秘密が掘り起こされる。64を解決に導こうと警察庁長官が、形だけの現地視察をしようとした日に新たな事件が発生する。
それは未解決事件64を明らかに模倣していた。
本書の舞台である未解決事件『64』(通称:ロクヨン)をめぐる人間模様、心の葛藤は警察を舞台にしているだけに重く、ふだんわたしたちの身にのしかかってくる責任の大きさとは比べ物にならない。
しかし、主人公の警察広報官である三上の心の揺れはわたしたちそのものである。
警察という巨大な組織の一端をみた気がするが、それが自分自身の所属する小さな組織と抱えている問題は多かれ少なかれ変わらない。
三上は警察という組織に守られている。心は複雑で、警察組織に対して感謝だけでなく敵対心も同時に感じている。
刑事という職を取り上げられ、現在の広報官になってからは、マスコミに対しての不信感もあり、それが自分の所属する組織警察への不信感にも繋がっている。
客の相手がいやになり、勤めている会社自体がいやになるという構図、しかしその会社に自分は守られている。一筋縄ではいかない。読者は自分の所属する組織に置き換えて考えてしまうのではないか。
64の被害者家族として雨宮という人物が登場する。誘拐され殺された少女の父親である。
雨宮の心の動きが主人公の三上には読めない。読者も「なぜ?」を包有したまま置いていかれる。
雨宮はすでに生きる気力をなくした人間に映る。
本書には、生きる気力をなくした人々が多く登場する。すべてこの未解決事件64に関係している。
傍目には「生きる気力をなくした人」に映る人々が、実は多くのものを内包していることに気づかされる。
そして傍目には「生きる気力をなくした人」として見えている人物が実は別のことに生きる力を使っているということに改めて気づかされる。執念というものはそういうものかと。
組織の中で自分を守ろうという執念。未解決事件を追う刑事の執念。被害者家族の執念。犯人の執念。
本書の最後にくるのは、人を愛することの執念だろうか。
『64』は、最後の最後まで、読者を引きつけて生きていくことの意味を問う第1級の小説である。
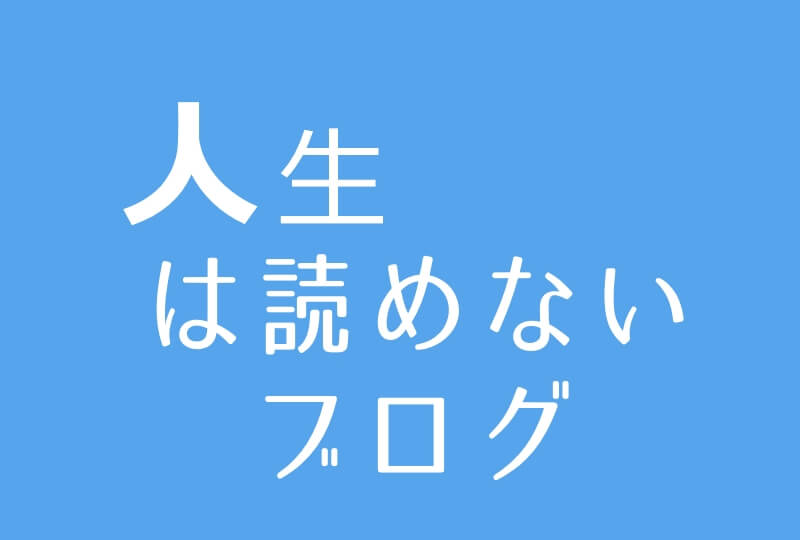


コメント