眉山
さだまさし(著)

徳島で初めてこの山の名前を目にした時、<マユヤマ>と読んだ。
取り立てて高い山でもなく、長野育ちのわたしからすると大した山には思えなかったが、地元徳島で、眉山はシンボルである。
日本でいうなら富士山ということになる。
さだまさしが書いた小説だからこの本を読んだというわけではない。
この本を手にしたのは、わたしが徳島に住んでいた事があり、タイトルの眉山を良く知っていたからである。
眉山をはじめ吉野川、阿波踊り、秋田町など実際の風物詩や地名がところどころに登場する。あらためて思い出したのは徳島弁だ。
どちらかというと関西なまりなのだが、徳島ではなぜか女の人だけが使う言葉というか言い回しがある。
言葉の終わりに「〜じょ」をつける言い回しだ。
例えば、
「電話したんじょ」
初めて聞いたときに、かわいい言い回しだと思った。
注意して聞いていると、男性は「〜じょ」をつけて言わない。女性の場合は直前の言葉によっては最後に「じょ」がつくことが分かった。
『眉山』の中のセリフで言うと、
「ほなけど、一杯目だけにしとき。これだとかぁるいけん、ついつい、飲みすぎるんじょ」
といった具合だ。
本小説でのセリフは、徳島弁が全開でついつい話に臨場感があって引き込まれてしまう。方言というものには心を伝えるライブ感があると思う。
主人公の咲子は、父親の記憶を知らない。母は父親の話をみずから咲子に話すことはない。母は咲子を生むために親元を離れて徳島にきたらしい。
徳島の夜の街で母は自分の店をもつまでになり、人によれば徳島一の人気店らしい。
そんな母が店をたたむことになる。咲子と母にとって来るべきときがきたのだ。
余命いくばくかの母は、最後の阿波踊りまでの間、咲子に自らの生き方を無言で伝えていく。
あらすじからすれば、悲しくなる内容だが、読んでいて全くそういったことは感じない。それも魅力あるキャラクターたちのせいだ。
“神田のお龍”こと母の切符のいいものいいは、病人である湿っぽさを感じない。
ケアハウスで母の世話をする啓子。
母の店の常連客で母を“神田のお龍”さんと慕う賢一。
常識知らずの若い研修医寺澤。
みなが主人公咲子の母を中心になりたっている。最後まで咲子は父のことを母から聞き出せない。
最後に母が咲子に伝えたかったことはなんだろうか。
物語は、最初はいやなやつだった研修医寺澤の学生時代の作文で終わっている。
たぶん、何の前ふりもなしにその作文だけを読むと「まあ、そうだね」と感じるだけだろう。
しかし、この物語を読んだ後だと泣けてくる。心に浸みてくるのだ。
賢一が咲子の母“神田のお龍”から怒られたときの言葉、
「いいかいまっちゃん、孝行はね、親が生きているうち、じゃあ遅すぎるんだよ。
親がねぇ、元気でいるうちにしなきゃあ駄目だよ」
はわたし自身の心にも響いた。
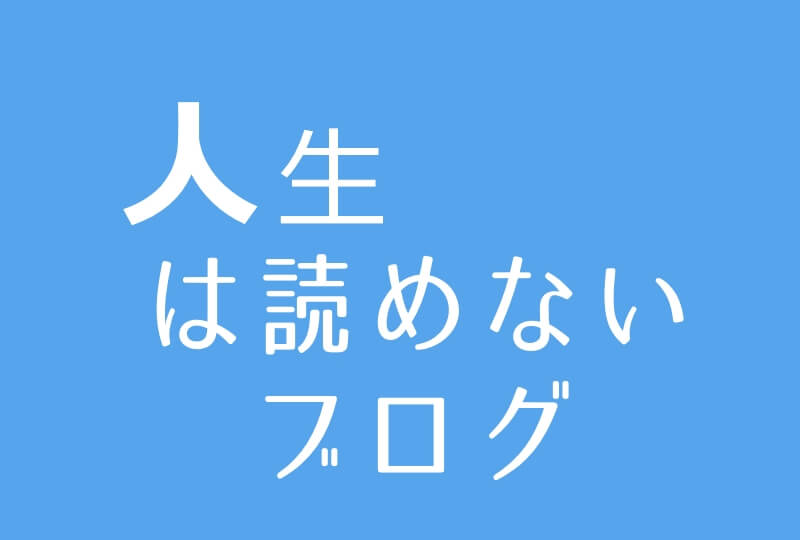

コメント