「頭を使った体育会系」
この小説を一言で表すなら、こんな言葉になる。
天地明察
冲方丁(著)

江戸時代の話だ。
『明察』(めいさつ)、『誤謬』(ごびゅう)、『必至』(ひっし)など主人公を中心に使われる言葉の数々が読後に口ずさみたくなる。
天地明察で登場するこれらの言葉を、普段の生活においても使ってみたいと思ってしまうくらいに恰好良い。
主人公の渋川春海が幕府から命を受け携わった「日本独自の暦を作り上げること」。
この壮大なプロジェクトを巡り多くの人々が一つに収束していく四半世紀にわたる物語が『天地明察』だ。
上下巻合わせて556ページのボリュームだが、読みやすい。
ただ、わたしがここで「日本独自の暦を作り上げること」がどれだけ凄いことかを説明しても面白くもなんともない。
この小説を読む事がそれを証明してくれているからだ。
「月の満ち欠け」がなんで予想出来るのか?その計算式はどうやって立てたのか?を考えてみると少し凄さが分かるかもしれない。
暦についてこんな記述がある。
暦は約束だった。泰平の世における無言の誓いと言ってよかった。
“明日も生きている”
“明日もこの世はある”
天地において為政者が、人と人とが、暗黙のうちに交わすそうした約束が暦なのだ。
それは万人の生活を映す鏡であり、尺度であり、天体の運行という巨大な事象がもたらしてくれる、“昨日が今日へ、今日が明日へ、ずっと続いてゆく”という、人間にとってなくてはならない確信への賜物だった。
わたしたちがふだん何の疑いもなく使っているカレンダーは、そういうことだったのか、と思う。
小説の良い所は「日常に疑いをもつ」ことなのだと感じる。
最初に、この小説は「頭を使った体育会系」だ、と書いた。
算術(今でいう数学)は当時は娯楽の一つでもあった、と小説の中にある。
算術を学んだものが、試しとばかりに神社の絵馬に問題を書いて出題し、それを見た誰かが絵馬に解答する。
正解なら『明察』、不正解なら『誤謬』。
勝負の仕方が爽やかだ。
主人公の春海は、ライバルでもあり、目指すところでもある関孝和に対し、正解が無い設問である『無術』の問題を出題してしまい、赤っ恥をかいてしまう。
プロジェクトの方も失敗し失敗し失敗する。
それでも人生をかけた勝負は一度では終わらない。投げ出さず、諦めない姿勢が主人公の春海にはある。
「頭を使った体育会系」という表現が正しいかどうかは分からないが、スポーツの世界のように爽やかさが残る小説である。
一つ付け加えるならば、この人生を懸けた大勝負には老若男女様々な人が登場している。
特に50も60も過ぎた年の人たちが春海に教えを乞うたり、あるいは手助けしたりする場面がいくつもあるのだ。
「学ぶのに遅すぎることはない」という言葉があるが、『天地明察』を読んで爽やかな印象を受けるのは、きっとこの言葉の持つ意味を登場人物を通じて表現しているからかもしれない。
「今がその時!」と後押しされた、そんな気分になる。

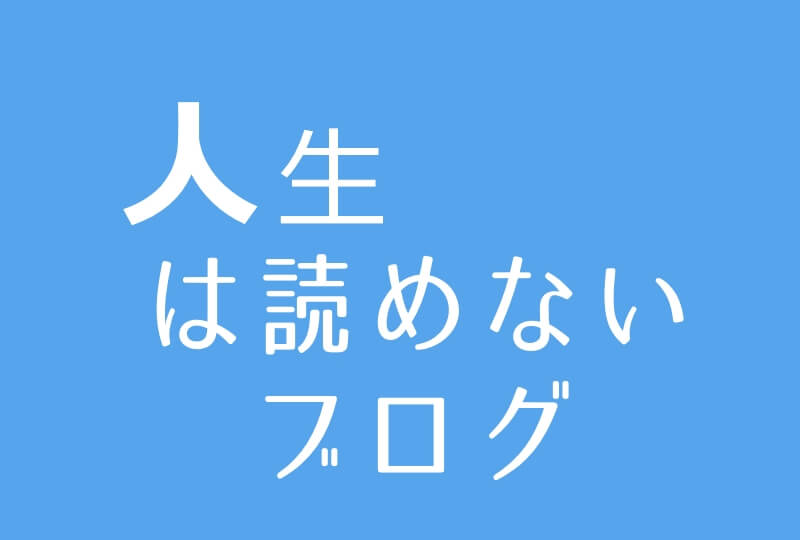

コメント