九月が永遠に続けば
沼田まほかる(著)
沼田まほかるのデビュー作。
しかし、人間とは何と無力なのだろうか。
わたしが手にしている文庫本の版数は、22刷である。発売から約4年で。
事前知識なしに本作を読めば、誰しも「九月が永遠に続けば」がデビュー作品などとは思わないはずだ。
また本作品の肩書き「ホラーサスペンス大賞」を知らずに読めば、本作がホラー作品というジャンルをかるく越えていることに気づく。わたしは、<人間のもつ無力さ>をあえて沼田まほかるは提示したかったのではないかと思う。
夜、ゴミ捨てに出かけた主人公佐知子の一人息子<文彦>が失踪する。文彦は高校生だ。佐知子には、原因が分からない。佐知子は、八年前に夫<雄一郎>と分かれた。今は、教習所の教官である<犀田>とつきあっている。つきあっているというより、心のすき間を身体で埋め合わせている状態だ。しかも犀田は、元夫雄一郎の再婚相手<亜沙実>の娘である<冬子>と恋人関係にあるようだ。
息子の文彦が失踪した翌日、犀田が謎の死をとげる。冒頭から翌日までの展開は、じわじわと恐怖が押し寄せてくる。この辺りは、ホラーだろう。
ここから物語は、これでもか、これでもかという<絶望>が押し寄せる。
今まで何の変哲もなく過ごしていた日常が一変する、という定番的な話を<ホラー>から<人間とは>に状態を変えじょじょに切り替えていく展開はデビュー作とは思えない。
文章力があるというのは、こういうことを言うのかなと思う。
「九月が永遠に続けば」では、一つの文をとって意識的に読んでみるとかなり作りこまれていることが分かる。
けれども現実には、街角をひとつ曲がるほどのたやすさで、 誰でも<そういう種類のこと>の内部に迷い込んでしまうものなのらしい。 足元にまとわりつく猫につまずきながら朝食をつくるあわただしい朝や...
気がつくとある日、私は十七歳だった。ある日二十五歳だった。ある日三十歳だった。 そして今日、気がつくと四十をひとつ過ぎていて、眉を描きながらため息をつくのが癖に なっている。 きっといつか同じように、死の床に横たわる自分にふと気づくのだろうか。
わたしたちは本を読むとき、一字一句見逃さずに本を読んでいるわけではない。
文章のもつリズムや、場面場面で使われる言葉によってイメージする。本を飛ばし飛ばし読んでいるようなものだ。それでもなお、キャラクターの造詣や次第次第に変化する心情が手に取るように分かるのであれば、その文章は完成されているのだ。飛ばしながら読んでもハッとするように。
「九月が永遠に続けば」は、慰めにならない物語であるにも関わらず、つい引き込まれるのはなぜだろうか。
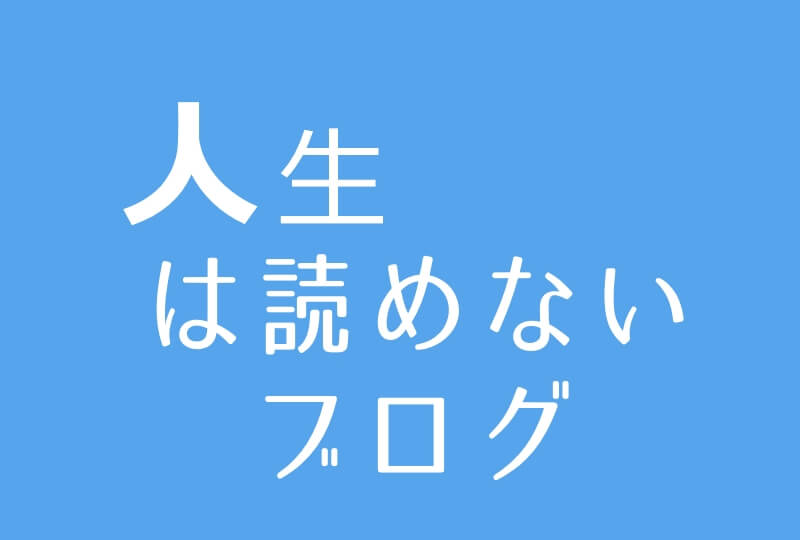



コメント